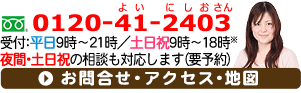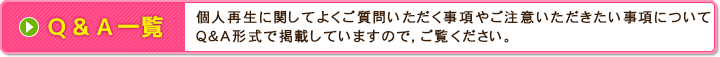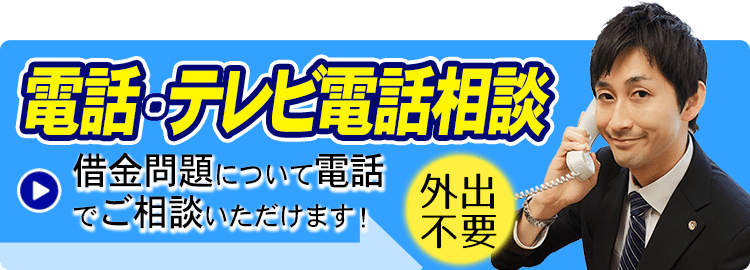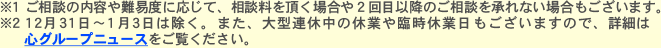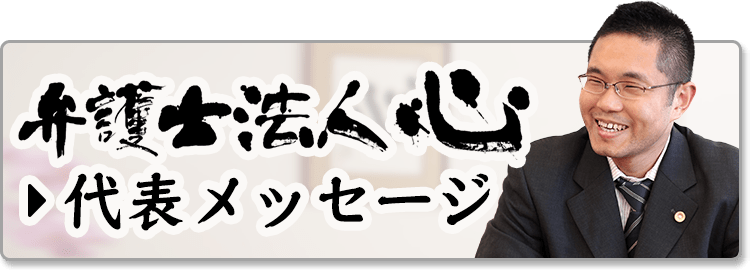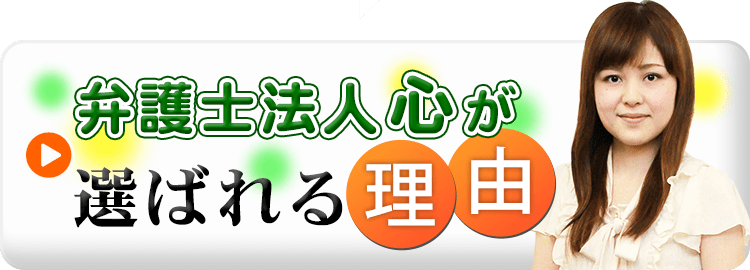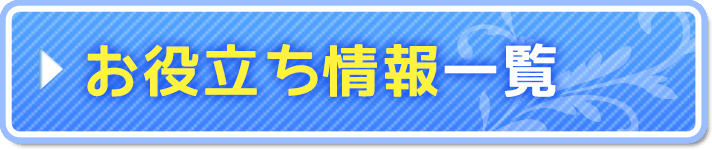「個人再生ができるための条件」に関するお役立ち情報
個人再生に必要な条件とその手続き方法
1 個人再生手続きを利用できる条件
⑴ 債務者が個人(自然人)であること
個人再生は個人の債務者のみが利用可能です。
個人事業主は利用可能ですが、株式会社、有限会社など、いわゆる法人は利用することができません。
個人再生は民事再生手続きの例外として、比較的債務が少額で収支や財産の内容が複雑ではないと考えられる小規模な個人事業者、および給与所得者による利用を想定して設けられた制度であるためです。
⑵ 債務総額が5000万円以下であること
個人再生は、債務総額が5000万円以下の場合のみ利用できます。
債務の総額には利息や遅延損害金も含みますので、債務の元本が大きい場合には想定外に債務総額が増える可能性があることに注意が必要です。
債務の総額には、住宅資金貸付債権(住宅ローン)の債務額や、抵当権などの別除権付き債権おいて別除権行使により弁済を受けることが見込まれる金額は含まれません。
個人再生の申立て時点では債務総額が5000万円以下であっても、再生計画認可時に5000万円を超えた場合、再生計画が認可されませんので注意が必要です。
⑶ 継続的な収入を得て返済できる見込みがある
個人再生は、債務総額を大幅に減額できる可能性がある手続きであり、減額された債務を、再生計画に基づいて3~5年間で分割返済をすることになります。
分割返済をすることが前提となっているため、将来的に継続的な返済が可能であるといえなければ再生計画は認可されません。
毎月一定額の給与収入があるサラリーマンの方の場合には、この要件を満たすことが多いと考えられます。
個人事業者の方であっても、収入が安定していて、将来的にも大きな変動が起きる可能性が低いと考えられる場合には、問題ないと判断できます。
2 個人再生の手続きの方法
⑴ 個人再生申立ての準備
個人再生の申立てをするためには、様々な書類の作成、資料の収集が必要となります。
個人再生の申立書のほか、陳述書、財産目録、申立て前数か月分の家計表を作成します。
保有している財産や収支を裏付ける資料として、預貯金通帳の写し、不動産の登記と査定書、保険の解約返戻金計算書、有価証券の残高証明書、自動車の車検証と査定書、退職金見込額証明書、給与明細、源泉徴収票、大きな出費の領収書などを収集します。
これらの準備が整い次第、裁判所に個人再生の申立てをします。
⑵ 個人再生申立て~再生計画認可
個人再生を申立てると、まずは裁判所による書類内容の確認が行われます。
書類の内容等について裁判所から質問がされることがありますので、しっかりと対応をし、必要であれば追加資料も提出します。
書類等に問題がないと判断されたら、再生手続きが開始されます。
事案の内容や裁判所の運用によっては、再生委員が選任されることもあります。
その後、履行テスト、清算価値の算定、再生計画案の提出、債権者に対する意見照会を経て、問題がなければ再生計画が認可されて終了します。
小規模個人再生と給与所得者等再生 住宅資金特別条項を利用できない場合